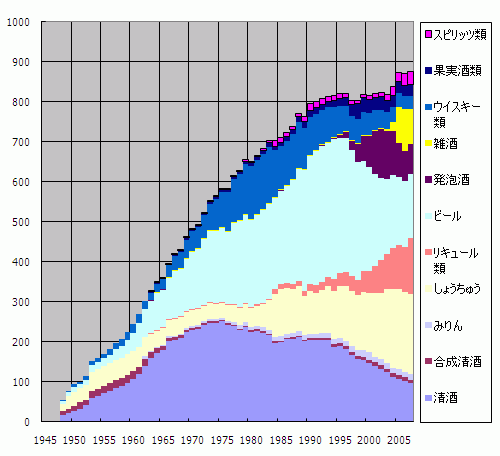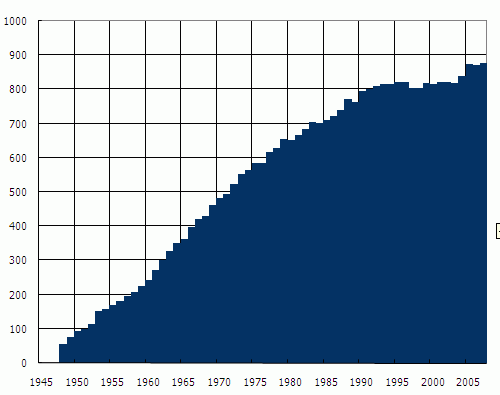少量から中等量の飲酒で、重度の認知機能低下のリスク低下なし。http://blog.livedoor.jp/ytsubono/archives/51847511.html (
魚拓)
著者らによると、先行研究の一部では、少量から中等量の飲酒による認知症や認知機能の低下を認めている。しかしこれらの研究の大半では、非飲酒者と過去飲酒者を区別せずに「非飲酒者」とし、このグループを基準群として、少量から中等量の飲酒のリスクを比べ、リスク低下を認めている。
しかし、過去飲酒者は病気や障害が原因で飲酒を止めた高リスク群が含まれているため、過去飲酒者を非飲酒者と区別せずに基準群とすることで、少量から中等量の飲酒のリスク低下を過大評価している可能性がある。実際、著者らのデータでも、過去飲酒者と非飲酒者をまとめて基準群とすると、男性の中等量飲酒者(一日24-40g)で誤差範囲を超えるリスクの低下を認めたという。
⇒少量から中等量の飲酒の影響を調べる際に、非飲酒者と過去飲酒者を区別して非飲酒者を基準群とすることの重要性を指摘した研究。
飲酒量と死亡率の相関関係をグラフにすると、「適量飲酒をしている者が最も死亡率が低い」という結果が出ます。グラフがJの字型になるのでJカーブ効果と呼ばれます。(Jカーブ効果は経済用語でもあるので、検索するときは「Jカーブ効果+飲酒」で)。
これによれば、禁酒は体に悪く、酒は少々たしなんだ方が健康に良い、ということになります。これは酒類業界にとっても、また税収を期待する政府にとっても都合の良い話です。
そもそもこの話は、アメリカで1993年に発表された結果が元になっているのですが、その研究では非飲酒群について、元から酒を飲まない人(非飲酒者)と、過去には酒を飲んでいたが酒をやめた人(過去飲酒者)が混ざっていました。過去飲酒者は(アルコール依存症とは限らないが)何らかの健康上の理由があって酒をやめた人たちで、死亡率を押し上げる要因となります。このため、その後あちこちで追試が行われています。
この研究では、過去飲酒者と非飲酒者を区別して評価した場合と、区別しない場合とで違った結果を導いています。つまりJカーブ効果を否定しています。
この問題については継続的に関心を持っていますが、僕の知る限り最近の研究結果ではJカーブ効果を否定する結果もあり、肯定する結果もありです。Jカーブ効果が否定されてしまうと、酒造業がたばこ産業と同じ立場に立たされてしまう危機感もあると思われます。
離婚は地球環境をさらに悪化させる=豪上院議員http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-36674420090225 [キャンベラ 24日 ロイター] オーストラリアのスティーブ・フィールディング上院議員は24日、議会の環境問題に関する公聴会で、離婚は地球の気候変動をさらに悪化させるだけだと発言した。
AAP通信によると、フィールディング上院議員は、夫婦が別離することによってより多くの部屋や電気、水が必要になり、結果的に二酸化炭素排出量が増えるとの見方を示した。
同議員は「(離婚という)社会問題があることを理解しているが、現在は環境面での影響もあることが分かっている」と発言。離婚による「資源非効率的なライフスタイル」を考慮すると、地球環境にとっては結婚生活を続ける方が良いと述べた。
少数政党の家族第一党を率いるフィールディング議員のウェブサイトによると、同議員は16人の子どもがいる家庭で育ち、現在は結婚生活22年目だという。
そう言われてもなぁ・・・。独身は地球環境に悪いので、皆さん早く結婚しなさいってこと?
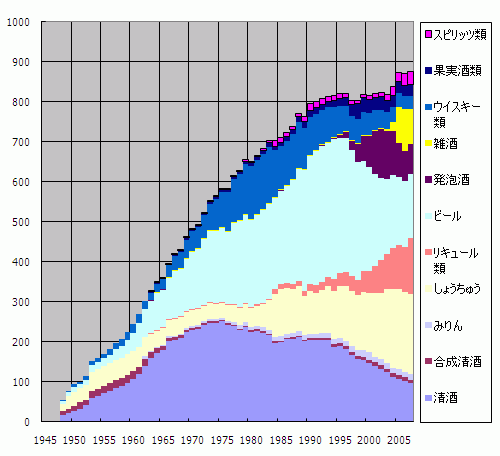
純アルコール消費量のグラフを、酒類別に色塗りしてみました。
酒類ごとの平均アルコール度数は発表がないので、適当な数字を使いました。
清酒(合成清酒)15%、しょうちゅう20%、ビールと発泡酒5%、リキュール類15%、雑種15%、ウィスキー類37%、みりん14%、果樹酒類12%、スピリッツ類37%。
どうして純アルコールに換算するかというと、清酒一合とビール大瓶一本がほぼ同じアルコール量なのに、容量が3倍も違ったりするからです。
1980年代以降にリキュール類が増えているのは、缶チューハイの登場。
一度増えた発泡酒が減りだしたのは増税のせい。
雑酒には「第3のビール」が含まれます。これはエンドウ豆とかが原料のヤツ。
同じ「第3のビール」でも、ビールにアルコールを足したいわゆる「第4のビール」はリキュール類に分類されます。
日本人は安酒をたくさん飲むようになったことが見てとれます。
国税庁が酒類別に消費量を発表しているので、それにアルコール度数をかけ、総アルコール消費量を計算してグラフにしてみました。
横軸は年で1947~2007年度。
縦軸は総アルコール消費量で、単位は千キロリットル。
バブル崩壊後、ちょっと減った時期もありましたが、ほぼ一貫して増え続けています。特にここ数年は大きく伸びています。
国民の総アルコール消費量と、その国のアルコール依存症者数は、比例することが知られています。
消費量が増えたからといって、すぐに依存症者が増えるわけではありません(病気になるには何年か飲み続ける必要がありますから)。でも、このデータを見る限り、日本人の飲酒量は減っておらず、増えております。
当然アルコール依存症者も増えていることが予想されます。
(酒類別のアルコール度数を変更したため、グラフも更新しました)
!たばこが原因で死亡、年間20万人 対策に増税必要?
http://www.asahi.com/health/news/TKY200812210181.html
たばこが原因で病気になり、死亡する人は、年間20万人近くにのぼるとみられることが、厚生労働省研究班(主任研究者=祖父江友孝・国立がんセンター部長)の調査でわかった。研究班は「健康対策として、増税を含めたたばこ対策がもっと必要だ」と指摘している。
国内の四つの疫学調査データを解析した。80〜90年代に40〜79歳の男女約29万7千人に喫煙習慣などを尋ね、約10年間追跡。2万5700人が死亡していた。喫煙率は男性54%、女性8%。
たばこを吸っていて病気で亡くなるリスクを、吸わない人と比べると、男性では(1)消化性潰瘍(かいよう)(胃潰瘍、十二指腸潰瘍)7.1倍(2)喉頭(こうとう)がん5.5倍(3)肺がん4.8倍(4)くも膜下出血2.3倍。女性では(1)肺がん3.9倍(2)慢性閉塞(へいそく)性肺疾患(COPD)3.6倍(3)心筋梗塞(こうそく)3倍(4)子宮頸(けい)がん2.3倍などだった。
また、過去に喫煙歴がある人も含めると、男性のうち27.8%、女性の6.7%が、たばこに関連した病気で死亡していた。
こうしたデータをもとに、05年の死亡統計にあてはめて計算すると、年間死亡者108万4千人のうち、たばこ関連の死亡者は男性16万3千人、女性3万3千人。05年時点の喫煙率は男性39%、女性11%のため、たばこに関連した病気になり死亡する人は今後、男性で減り、女性で増えると予想される。
解析の中心となった同センターの片野田耕太・がん対策情報センター研究員は「増税のほか禁煙治療をもっと広めるなど、総合的な対策を進める必要がある」と話している。(田村建二)
たしかに、大きく増税すれば喫煙は減るでしょうが、後期高齢者医療制度の話を持ち出すまでもなく、政府は国民に長生きして欲しくないので、税収が増える程度の増税しかしたがらないのではないかと。
!牛のげっぷ無視できない 温室効果ガス急増を予測
http://sankei.jp.msn.com/science/science/081210/scn0812100939001-n1.htm
気候変動枠組み条約事務局の報告書。牛のげっぷや水田などから出るメタン、窒素肥料の大量使用によって発生する一酸化二窒素など、農畜産業から出る温室効果ガスの量は世界全体の10-12%を占め、対策を取らなければ今後も急増が予測される。
温暖化防止には肉食をやめればいい、と言って叩かれていたイギリスのお偉いさんがいました。
これからは水田も「一酸化二窒素の排出源」と叩かれる時代がくるのかも。
!不幸な人ほどテレビを多く見る、米研究者が研究発表
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200811182324
社会的に恵まれないことが、すなわち不幸であるとは思わないですが、それはともかく。ケータイ、インターネット、テレビが「貧者の3大娯楽」と呼ばれて久しいわけです。
ケータイの使い方が、通話から通信(メールやネット)に移行しているのも、時間と費用が比例する通話より、定額制のパケット通信にシフトしているから。
インターネットが家庭に普及したのも、定額制のADSLに移行してから。
テレビは昔ながらでありますが、費用の発生するスカパーなどは流行っていません。
僕はテレビすら買えないわけですが。