12ステップのスタディ (38) OAのステップ2
おかげをもちまして、5月31日~6月1日に大阪で開催した Big Book スタディは55名の参加をいただき、無事開催できました。家族やACの方が多かったので、共依存についての説明にかなりの時間を割きました。参加された方や実行委員会の皆様に感謝申し上げます。
さて、今回はOAのステップ2です。
OAのステップ2は「自分を超えた大きなカが、私たちを健康な心に戻してくれると信じるようになった」となっています。1)
コンパルジョン
この「健康な心」は、すなわち「正気(sanity)」のことです。前回も書きましたが、自分を正気に戻してくれると信じるためには、まず自分が狂気を抱えていることを認めなければなりません。OAのテキストにもこうあります:
私たちのような強迫的なオーバーイーターの多くは、このステップを読んでこんな気持ちになる。「自分を健康な心(正気)に戻す必要なんてない。私はまったく健康で、ただ食べ方だけが問題なのだから」。でも果たして、私たちの心はどれだけ健康なのだろうか。2)
ステップ1が十分にできているのならば、ステップ2で改めて自分の心の狂気について確認し直す必要はないはずですが、12ステップのテキストの多くは、ステップ2で自分たちが狂気を抱えていることを改めて指摘してきます。それは、ステップ1の振り返りを行う必要があるということです。またそれは逆に、いかにステップ1が疎かになりやすいかを示しているとも言えます。
先ほどの続きです:
徹底的に正直になって自分の生き方を見つめてみれば、食べ物に関するかぎり、私たちはきわめて筋のとおらない自己破壊的な行動を取っていたことがよくわかる。何が何でも食べたいという強迫観念に襲われると、分別のある人ならとても考えつかないようなことまでやっていた。2)
アルコホーリクは酒を求めて、普通の人なら考えつかないようなことをします。前の連載の第115回で紹介した映画『酒とバラの日々 』では、酔っ払った主人公ジョーが酒を求めて深夜の街をさまよい歩き、酒屋の主人を起こそうと閉まっている店の扉を叩くシーンがあります。また、農園の温室に隠した酒を探したのに見つけられず、苛立って温室の中の花を滅茶苦茶にしてしまうシーンもあります。同じようにアディクトはクスリを求めて普通の人なら考えつかないようなことをします。共通しているのは、そういった行動を取っているときのアル中・ヤク中はコンパルジョンに支配されている点です。
そして、同じようにコンパルジョンに支配されているときのオーバーイーターも、普通の人なら考えつかないようなことをします。スーパーから10キロの米袋を担いで万引きした話だとか、深夜に隣家の台所に忍び込んで冷蔵庫を漁っていたら見つかってしまった話などを聞くと、「摂食の人たちもなかなかやるもんだな」と思います。
オブセッション
ただこれらは、食べることによってコンパルジョンが生じてきた「後」のことです。食べる「前」に起きるオブセッションについては、こう述べています:
悩みの種は、強迫的な食べ方がひどくなるにつれて満足感が得にくく(never=得られなく)なったことだった。食べることに慰められるどころか、むしろその逆で、食べれば食べるほど苦しみは増した。それでも私たちは食べ続けた。私たちの本当の狂気とは、強迫的な食べ方がだいぶ以前から悲劇の原因になっているにもかかわらず、それでもなお食べ物に慰めを見いだそうと脇目もふらずに突っ走ったことだ。3)
アルコールや薬物を習慣的に使う人は、それに何らかの効用を見いだしています。それはストレスからの解放や気分転換などです。その人はアルコールや薬物を使うことで、ストレスや気分の問題を「解決」しているわけです。使用によって大きなトラブルが起きないのであれば、その人はアルコールや薬物から効用だけを得ていることになります。それが普通の酒飲みであり、普通の薬物ユーザーというものです。
ところが、そのなかの一部の人たちが、ある特殊な体質(シルクワース医師がアレルギー体質と呼んだもの)を持っていると、やがてアルコールや薬物の使用がコンパルジョン(強迫的欲求)を引き起こすようになり、コントロールが効かなくなって、アルコールや薬物を過剰使用するようになります。そしてこの過剰使用が、身体的・精神的・社会的なトラブルを引き起こし、その人が後悔したり、周囲から非難されたりする原因となります。(つまりかつては「解決」であったものが「問題」に化けてしまうのです)。
不思議なことに、このコンパルジョンが生じてくるようになると、最初の頃に得られていた効用は次第に得にくくなっていきます。アルコールや薬物は変わらずに酩酊や興奮をもたらしてくれものの、求めている気分の変化(陶酔感や高揚感)はなかなか得られなくなり、しまいには全く得られなくなります。つまり、メリットが無く、デメリットばかりが目立つようになります。アルコールや薬物を使うことが損失しかもたらさなくなるので、その人は、「もう二度と使わない」と誓うのですが、しばらくすると再び酒や薬物を使い始めてしまいます。これがアディクト(アルコホーリク)の持っている狂気(強迫観念)というものです。
OAのテキストは、これと同じことが強迫的オーバーイーターにも起きていると述べています。誰でも、美味しいものを食べたときには満足感や心地好さを味わうものです。そして、食べることで、ストレスの解消や気分の問題の解決をする人たちもいます。それによって大きなトラブルが起きないのであれば、その人たちは食べ物から効用だけを得ていることになります。
ところが、そのなかの、ある特殊な体質を持っている一部の人たちは、やがて食べることがコンパルジョン(強迫的欲求)を引き起こすようになり、食事のコントロールが効かなくなって、過剰に食べるようになってしまいます。そしてこの過食が、身体的・精神的・社会的なトラブルを引き起こし、その人が後悔したり、周囲から非難されたりする原因となります。(解決の問題化が起こる)。
そして食べ物の場合もアルコールや薬物と同じように、コンパルジョンが起きるようになると、当初に得られていた効用が得られなくなります。つまり、求めている気分の変化(陶酔感)は得られなくなり、満腹や嘔吐の苦しさや過食することの罪悪感ばかりが残ることになります。メリットが無く、デメリットばかりが目立つようになるので、その人はもう二度と過食はしないと心に決めるのですが、しばらくすると再び過食を始めてしまいます。これが強迫的オーバーイーターの持っている狂気(強迫観念)というものです。
共依存の問題
第28回で、OAのステップ1は食べ方の問題だけでなく、共依存の問題を認めるステップになっていると説明しました。強迫的オーバーイーターは、自分の周囲の人やものごとを自分の思い通りにコントロールしようとし、(当然そんなことがうまくいくはずはないので)それに失敗すると、それによって生じてくる不安や失望や怒りを解消するために過食という手段を使ってきた、と指摘していました。
それは「周りの人々やものごとが自分の思い通りになってくれれば自分の心が平和になり幸福になれるのだ」という考え方を持っているということであり、その考え方が変わらない限り、感情的な危機が繰り返され、オブセッションによって再び強迫的過食へと戻っていってしまいます。
なのに、自分がこの共依存の問題を抱えていることを認めないオーバーイーターも少なくありません。OAのテキストもこう述べています:
私たちのなかには、強迫的な食べ方はひとりでいるときしかしなかったし、それ以外は比較的、普通の生活を送っていたという仲間も多い。昼間は必死で仕事をし、夜になると必死で食べた。確かに、多くの点では分別があった。3)
つまり食べ方だけが問題なのであって、「生き方の問題」などは抱えていないという主張です。そこでOAのテキストは、自分の生き方を振り返って見るように勧めます:
だが、引き続きよくよく省みたところ、いろいろな部分で生き方のバランスが取れていなかった。たとえば、自分の子どもたちがかまって欲しくてまつわりついてくると怒鳴りつけた。配偶者にほかの異性の影が見えようものなら、嫉妬のあまりに分別があるとは言いがたい態度をとった。私たちは長い間、恐れと不安のなかで生きてきた。4)
このあとまるまる1ページを費やして共依存の例示がなされるのですが、それは「あなたが不安と不満のなかで生きてきたのは、なにもかも自分の思い通りにしようとしているからではないか」と問いかけているのです。そして、その結論は:
私たちがこれほど苦しんだのは、自分の生き方そのものが原因だったことが、少しずつわかってきた。自分が変わる必要があるのだ、と徐々に信じられるようにもなった。だが私たちは、食べ物のことだけでなく、生活のあらゆる面で理性を欠き、バランスを失い、分別がなかった(insane=狂気)のだ。だから、いくら意志を強くしても、いくら固い決意をしても、自分の生き方がうまくいくことはなかった。5)
OAのステップ1は、食べ物の問題だけに狂気を抱えていたのではなく、それ以外のことでも自分は狂った生き方をしていたのだ、と認めるものになっています。
・・というわけで、ここまでがステップ1の振り返りです。OAのテキストはステップ2に11ページ半を割いていますが、実にその半分がステップ1の振り返りに費やされています。
その力が正気に戻してくれる
OAのテキストの先ほどの続きです:
このまま変わらないのだとしたら、いったいどうすればよいのだろうか。このことから、健康な心(正気)を取り戻したいと本当に思うのなら、自分を超えた大きな力を見つけださなければならないことが明らかになった。5)
OAの12ステップでも、その力(=神)を見つければ、その力が問題を解決してくれると言っています。OAの12ステップも、自分で問題を解決する手段ではなく、何かに解決してもらう手段なのです。
自分よりも大きな力(ハイヤーパワー、神)
となると、では自分よりも偉大な力(ハイヤーパワー、神)と表現されているものは何者なのか? という疑問が生じてきます。これについてもAAの12ステップと同じです。つまり、OAでも、神の概念は、ステップに取り組む一人ひとりが自ら選び取るべきものになっています。
OAのテキストは、ビギナーにとって受け入れやすい神の概念の例を挙げています。その一つはOAグループ(の持っている愛)です。
ミーティング場には、私たちを理解し、思いやりを示してくれる仲間がいた。私たちは正直になって何もかも話したが、それでもみんなは無条件で受け入れてくれた。受け入れることは愛だった。その愛には、OAミーティングの会場を離れたあとも、いつも自分と共にあるのだと思える力があった。こうして分かち合われた愛情こそが私たちを超えた大きな力であり、その力が私たちを健康な心(正気)に戻してくれるのだと信じることは、それほど思い切りの要ることではなかった。このようにして、グループの愛情が私たちのハイヤー・パワーになった。6)
さらには、スポンサーという存在も最初のハイヤーパワーの概念として選び取りやすいと説明しています。7)
ハイヤー・パワーの概念は変化していくべき
さて、第36回で、
多くの人は、ステップ2で自分が信じられるハイヤーパワーの概念を選び取ることで、自分は「信じる」ということについてゴールに到達できたのだと勘違いしてしまいます。実際にはその人はまだスタートラインについただけです。
と書いたことをここで再び取り上げます。回復を続けるならば、そのスタートラインから離れて前に進んでいかなければなりません。つまり、その人の持つ神の概念が変化していかなければなりません。その変化はたいてい失望によってもたらされます。
だがOAメンバーも人間である。ときには自分のグループやスポンサーに失望することもある。そうなると、かけがえのない支援が断ち切られたようで、心の安らぎさえ脅かされたように思えるものだ。7)
そのような経験をした人は、OAグループやスポンサーは真のハイヤー・パワーではないことに気づきます。失望してもなお、ハイヤー・パワーを求め続けることで、その人はOAグループともスポンサーとも異なるハイヤー・パワーの概念を獲得することになります。それを繰り返すことで、回復とともにその人の神の概念(言い換えれば、神についての理解)が変化していくことになります。
したがって回復を続けているならば、いつまでも同じハイヤー・パワーを同じように信じ続けることはあり得ないわけですし、神への理解が深まっていかないのであれば、それは回復が進んでいないということでもあるのです。
ただ、ステップ2の段階では、そんな先のことまで心配する必要はありません。自分が信じることができる対象で、なおかつ自分より何らかの意味で大きく、自分の回復を導いてくれるものであれば、それを選び取れば良いのです。
- 健康な心を取り戻すには、まず自分の狂気を認めることが必要。
- オーバーイーターは、アル中やヤク中同様に、強迫的な欲求(コンパルジョン)に支配され、食べ物を得るために常識を逸脱した行動をとることがある。
- オーバーイーターは、初めは食べ物で感情を処理していたが、次第に効かなくなって苦しみと罪悪感だけが残るようになっているが(解決の問題化)、そうなるとわかっていても過食を始めてしまう(オブセッション)。
- 周囲をコントロールしようとする共依存的の生き方が、感情的な危機と過食を引き起こす根本原因であるとOAテキストは指摘している。
- 最初はOAグループやスポンサーなど、受け入れやすい対象をハイヤー・パワーと見なしてもかまわない。
- ただし、神の概念は、経験や失望を通じて変化・成長するものであり、いつまでも同じ理解にとどまるのは回復の停滞を意味する。8)
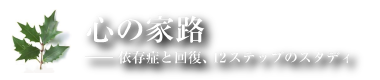


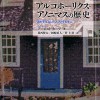
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません