群盲評象
霧の中を歩く
僕は長野県の田舎で生まれ育ちました。自宅から6年間通った小学校までは、およそ1.6Kmの道のりでした。家を出ればすぐに学校が見えたのですが、そこまで田んぼの中のまっすぐな道を1Km以上歩いて行かねばなりませんでした。春や秋の朝は濃霧が発生することが多く、視界が10メートル以下になることもしばしばありました。

濃霧に包まれると、自分を中心として半径10メートルぐらいの範囲しか見えなくなります。それより遠くは真っ白な霧の中です。ではあっても、毎日通っているまっすぐな道は迷いようがなく、いつも無事に学校に着いていました。
その道は多くの子が通学路に使っていましたから、僕の少し前にも、少し後ろにも、子供たちが歩いているのが見えました。その姿は霧に包まれて、僕のいる場所よりずっと濃い霧の中にいるように見えるのですが、その子たちも僕と同じように自分を中心として半径10メートルの範囲が見えているのでした。
もう少し大人になって、人間とか、人間の作った社会というものを考えるようになったとき、人は誰しも霧の中を歩いているのだと感じました。地球は大きく何十億という人が住んでいますが、人は皆ごく狭い範囲で生活を営み、ごく限られた人とつきあい、その外のことは経験できずにいます。本やテレビやネットを使って、その外側の情報を得ることはできますが、自分が受け取れるのはその一部分にすぎません。
僕の歩いていた通学路は、同じような四角い田んぼの連続でした。だから、自分の10メートルの視界の外側も、同じような風景が続いていると想像しても間違いではありませんでした。しかし、世界(あるいは社会)は田舎の田んぼのように均質ではないので、自分の視界に入る情報だけで、その外側を理解することはできません。
ジョー・マキューの言葉を紹介しましょう:
世の果てしない時間の広がりのなかでは、私たちの一生はほんの一瞬でしかない。それは目に見えないほどの点のようなものである。その短い期間、私たちはささやかな情報を集め、かぎられた教育を受けるが、人生を取り仕切る万能の情報を手に入れることは不可能である。・・・仮に、地球上のすべての知識をかき集め、それを一つの頭脳に詰め込んだとしても、それは神から見た知識にはとても届かない。だから、そのようなスーパー頭脳をつくったとしても、この世のことでわかるものはほんのわずかでしかない。このように考えてみれば、肩の力が抜けてほっとするのではないだろうか。1)
依存症という霧
僕は長野県のAAで15年ほど活動しました。それなりの経験を積んで、アルコホリズムとは何かを、おおよそ分かった気がしていました。
6年前にジョブチェンジをして、東京の施設で仕事をするようになり(もう辞めちゃいましたが)、同時に埼玉に越しました。仕事でもAAでも様々なアルコホーリクと関わるようになり、その多様性に気づかされました。それは、アルコホーリクの集まりには必ず偏りが生じると言い換えることもできます。
例えば、東京近辺にはアルコール病棟を持った病院が幾つもあります。仕事やAAでそうした病院に出入りし、入院患者さんたちと接していると、それぞれの病院が異なるタイプの患者さんを集めていることに気づきました。
具体的にどの病院にどんなタイプの人が多い、という説明は憚られるのですが、何も書かなければ読んでいる方がモヤモヤするだけでしょうから、例を挙げましょう。例えば、退院後に自助グループに通わず、通院もせず、すぐに再飲酒してしまうような治療意欲の薄い人を、何度も何度も入院させるかどうか。その方針は病院によって異なっています。
そういう人の入院を断るようにすれば、病棟における治療意欲の水準をある程度高く保つことができます。入院回数が少なく、家族や仕事をまだ失わないでいる人の比率が大きくなります。そこで仕事をしている医療スタッフが、そうした患者さんたちを見て「普通の人生の途中でこの病気に罹ってしまった不運な人たち」という視点を持つことはそれほど難しくはないでしょう。(もちろんアルコホーリクがラブリーということはあり得ないので、お仕事は大変でしょうけど)。
一方で生命予後を重視して、意欲の低い人たちも引き受ける病院はどうなるかというと、当然治療意欲の平均水準は下がり、入院を重ねている人が増え、仕事や家族のない人の割合も増えてきます。患者さんが医療スタッフに不満をぶつけることも増えます。こういう場所で仕事をしていると、「だらしない無気力な人たちが依存症になるのだ」という考えに傾きがちでしょう。それを考えれば、その現場から「どうせ依存症の人たちは酒を止めませんから」という厭世観溢れる言葉が飛び出してきたとしても、とくに驚くには値しません。
どちらが良いかという話ではなく、依存症の人といっても様々であり、様々な理由で偏りが生じうるということです。
AAもグループによって違いがあります。サラリーマンが多いグループもあれば、生活保護の人が多いグループもあります。12ステップに熱心なグループもあれば、ステップなんてやらなくて良いというグループもあります。ひとつのグループだけ経験して、「AAとはこういうものだ」とか「回復とはこういうものだ」という理解を得たとしても、それは偏りのあるサンプルから得られた理解に過ぎません。
人は自分の経験したことから帰納 的に法則を導き出して、何かを理解したつもりになります。しかし、その経験は霧の中の10メートルの視界の中のものにすぎず、また視界の先にも同じ風景が続いているとは限りません。場所が変わったり、時代が変わったりして、条件が変われば、その法則はとたんに通用しなくなります。
アルコールと違法薬物の重複しているケースでは、幼少時に虐待を受けている比率が高くなることが知られています(特に女性の場合にはその率が高くなる)。そういうケースにばかり接している人は、依存症は親の虐待が原因で生じる病気という考えを持ったりしますが、それも局所的な経験から導かれた理解にすぎません(被虐待は依存症になるリスクを高めるが、統計的には共有環境の影響は大きく現れない)。
長い期間にわたって生活保護を受けているアルコール依存症の人は、依存症以外にも別の困難(病気や障害など)を抱えていることが多いのですが、そうした偏りのおかげで、福祉事務所の生活保護のワーカーさんの中には、依存症だけ患っている人は存在しないと思っている人がいたりします。
「依存症の人は幼少時に虐待を受けている」とか「依存症は必ず他の障害と重複する」という法則は、ある限定されたグループを観察した結果導き出されたものです。そうした限定された条件での発見にも価値はあります。その発見に基づいて、何らかの対応策が編み出され、それが効果をもたらすということは、十分にあるでしょう。それは局所的な解(local solution)に過ぎないのかも知れませんが、役に立つというのなら否定されるべきではありません(cf. プラグマティズム)。
ただ、それが依存症全体に通用するわけではない、ということは気がついていなければなりません。
中井久夫 は『世に棲む患者』2)の対話編のなかで、「アルコール症は地域によって大違いだ。それによって治療法も変わってくると思う」と述べ、アルコール症者とその治療の地域差について説明しています。
群盲評象

群盲評象という言葉があります。ウィキペディアの説明によれば:
ジャイナ教の伝承では、6人の盲人が、ゾウに触れることで、それが何だと思うか問われる形になっている。足を触った盲人は「柱のようです」と答えた。尾を触った盲人は「綱のようです」と答えた。鼻を触った盲人は「木の枝のようです」と答えた。耳を触った盲人は「扇のようです」と答えた。腹を触った盲人は「壁のようです」と答えた。牙を触った盲人は「パイプのようです」と答えた。それを聞いた王は答えた。「あなた方は皆、正しい。あなた方の話が食い違っているのは、あなた方がゾウの異なる部分を触っているからです。ゾウは、あなた方の言う特徴を、全て備えているのです」と。3)
依存症はこの象であり、私たちはこの盲人でしかありません。象全体を見ることは誰にもできず、誰が何を主張していても、腹を触った者が「壁のようです」と語っているのと同じです。僕も象全体を見たいと強く願ったこともありましたが、やがて自分も盲の一人に過ぎない現実を受け止めざるを得なくなりました。
AAの方法論も、アルコール依存症という巨象の一部分だけを対象としたものです。それは地理的な条件ではなく、まずアルコホリズムとはこのような病気である(具体的には身体のアレルギーと精神の強迫観念)という定義を先に決めてしまい、その条件に当てはまる人たちを対象に12ステップという方法論を組み立ててあります。それは、巨象全体にはおそらく通用しないでしょう。AAはもちろんそのことを認識しています(第9回参照)。
群盲評象の図が頭に思い浮かんだのは、もう何年も前のことでした。その時僕は、アルコール関連のある学会の大会に参加していました。シンポジウム を聞いていたのですが、演者の発表の後で会場も交えたディスカッションが始まり、やがて依存症者の支援論が珍しく侃侃諤諤の議論になりました。意見の対立が収まらなかったのですが、それはそれぞれの先生が、自分の患者(クライアント)という集合から得られた知見を述べているからで、その集合が重なっていない以上、議論の決着が付くことはないからでした。その会場の中に座っていて、失礼ながら群盲評象の図が浮かんできてしまったわけです。
科学の方法論では、交絡を排して「これだけは確かに言える」という知見を積み上げていきます。象全体を見ようとするよりは、触れる範囲の研究を深めていきます。だから、サイエンティストは、守備範囲が重なっていれば侃侃諤諤の議論を行いますが、違う分野の議論には首を突っ込みません。そういう意味では科学者は自らが盲であることに自覚的だと言えます。だから僕があのシンポジウムで見た盛り上がり?は例外的な出来事だったのでしょう。
しかし、科学的方法論から一歩踏み出せば、様相は一変します。人は自らが象をなでる盲であることになかなか気づけません。依存症のことを分かったつもりになっている人は、象が見えているつもりなのです。まあ、誰もが中井久夫になれるわけではないのは当然ですが。
このブログで「医師の意見」の項が、ビッグブック以外のことをたくさん扱っていたのは、これが象の一部分に触れているだけであることを明らかにしておく必要があったからです。
僕は長野にいた頃より視野は広がったとは言えますが、依存症の全体像については語りようがありません。せいぜいその一部分(ビッグブックが本物のアルコホーリクと呼んでいる人たち)について歴史的に有効性が証明されている方法(12ステップ)とその関連情報について知っていることを伝えられるだけです。
僕はアルコホリズムを病気として扱っていますが、世の中には◯◯依存症は病気ではないと主張する人たちもいます(◯◯には様々なものが入る)。僕とその人たちの主張に矛盾はありません。なぜなら、それぞれが象の別の場所を触っているために、違った結論が導き出されただけなのですから。どちらの知見も、限定された条件下でしか成り立たないのは明らかですが、どちらも間違ってはいないはずです。まあ、依存症という象は大きくなりすぎたのかもしれません。
それにしても、(依存症に限らず)なぜ象が見えているという勘違いが生じるかと言えば、それは、
自分がどこにいるかを気にしなければ迷子になる事はできない。マーフィーの法則
ということなのでありましょう。
- ジョー・マキュー(依存症からの回復研究会訳)『回復の「ステップ」』, 依存症からの回復研究会, 2008, p.18[↩]
- 中井久夫『世に棲む患者―中井久夫コレクション』, 筑摩書房, 2011[↩]
- Wikipedia, 群盲象を評す (ja.wikipedia.org), 2020-3-23[↩]
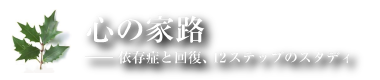
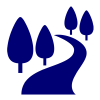



最近のコメント