12ステップのスタディ (34) ステップ1の振り返り
5月31日~6月1日に新大阪駅近くで Big Book スタディを開催します。最後に大阪で開催したのが2016年でしたから、実に9年ぶりです。僕が出張してのスタディを始めたのは15年ほど前のことで、当時はまだ40代でしたが、もう60代になってしまいました。呼んでくれる人がいる限り続けようと思っていますが、最近はさすがに体力的にきつくなってきました。
開催日までまだ間がありますが、残席が残り少なくなってきました(現在残り16)ので、参加を考えてらっしゃる方は早めに申込みをお願いします。なお、今回は二日間にわたる開催ですが、宿泊は参加者各自で手配していただくことになっています。大阪万博の開催期間中なので、早めに宿を確保したほうが良いかもしれません。
ステップ1の振り返り
前回で、AA・NA・OA・性・AC(共依存)という五つの分野のステップ1の説明が一巡しました。ここで、ステップ1を振り返ることにしましょう。
どこの共同体でもステップ1は「私たちは○○に対して無力であり、ライフがアンマネージャブルになっていたことを認めた」となっています。
ステップ1で必要なのは「認める」ことです。「認めた」という過去形になっているのは、12ステップの最初の解説本であるAAのビッグブックが、すでにアルコホリズムから回復していたAAメンバーたちが、彼らが回復するためにやったことを、回復を必要とする人に伝えるために書いた本だからです。1)
ですから、あなたが12ステップで回復したいのであれば、あなたも彼らと同じことをすれば良いのです。つまり、彼らがステップ1で何かを認めたのならば、自分も彼らと同じことを認めれば良いということになります。
では彼らはステップ1で何を認めたのでしょうか? 一つは、
-
- ○○に対して無力であること
です。この○○は共同体によって違いますが、AAの場合にはアルコホリズムという病気、NAの場合にはアディクションという病気、OAの場合には強迫的過食という病気、性の共同体では(それぞれ呼び方が異なりますが)性のアディクションという病気2)、そしてACの場合には共依存という病気です。
つまり「無力である」とは、自分ではその病気を解決できないことを意味します。そして、
-
- ライフがアンマネージャブルである
とは、自分の人生や生活が(時には生命までもが)その病気の深刻な悪影響を受けているということを意味します。
自分の抱えている病気のせいで、自分の人生や生活がダメージを受けているのに、それを自分では解決できないことを認めるのがステップ1です。
しかし実際にはそれを認めるのは難しいことです。その理由をいくつか説明しましょう。
意志の力は役に立たないのか?
人間は意志(will)を持っています。アルコホーリクが酒を止めるのに、意志の力(willpower、自制心)は役に立たないのでしょうか?
実際には意志の力は酒や薬をやめるのに役に立ちます。AAやNAは「24時間プラン」というものをメンバーに勧めています。これは「誰でも24時間だけなら酒や薬をやめ続けることができる」という考えにもとづいています。明日以降のことや一生やめ続けることなど考えずに、ともかく今日一日だけ酒(や薬)をやめるという実践です。『アルコホーリクス・アノニマスのマニュアル』の第3回で紹介したように、これは有名なマタイによる福音書 6:34の「明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である」(新共同訳)という宗教的な考えを応用したものです。
この24時間プランは明らかに「今日一日の断酒は自分の(意志の)力で成し遂げられる」という意味を含んでいます。つまりAAやNAは意志の力がある程度は有効であることを認めていて、それをそのプログラムの中に取り込んでいるのです。
しかし、前掲の『マニュアル』でも、AAの『どうやって飲まないでいるか』というテキストでも、24時間プランを説明する箇所で「明日は飲むかもしれない」と述べています。私たちの意志は「今日という一日」には及びますが、明日には及びません。つまり、24時間プランを使って今日一日の断酒を積み重ねる必要性を強調してはいるものの、それを続ければあなたは一生酒をやめ続けられる・・とはAAやNAは主張していないのです。3)
むしろその逆で、意志の力で一生やめ続けるのは無理だということ、意志の力には明らかに限界があることを教えてくれるのが、この24時間プランや今日一日という考え方です。
前掲のマタイ書の引用の途中に「明日のことは明日自らが思い悩む」とあります。これは、明日のことは明日になったら(あなた自身で)思い悩めばよい、という意味ではなく、明日のことは明日そのもの(tomorrow itself)が悩むという意味です。これは聖書特有の表現で、明日のことは神様が面倒見てくださる。だからあなた自身は明日のことを思い悩むべきではないという教えです。
つまるところ、いまこの瞬間飲まないでいることには意志の力が有効だけれど、明日の断酒は私たちの意志の力を超えているということであり、意志の力の限界を明らかにしているのです。
AAミーティングは役に立たないのか?
AAでは、酒をやめ続けるためにAAミーティングに出席することを勧めています。4)
しかし、なぜミーティングに効果があるのかについては、一つのことしか述べていません。それによればAAミーティングには回復へと向かいある種のモメンタム があるというのです(「弾み」と訳されている)。モメンタムとは、言わば「勢い」です。野球で、自分たちのチームの攻撃の時にヒットや四球が続き、どんどん点が入るときは、自分たちにモメンタムがある、と表現します。逆に、相手チームにモメンタムがあるときには、どんどん点を取られ続けてしまいます。その悪い流れを断ち切らないと、せっかく自分たちに攻撃の番が回ってきても三者凡退で終わってしまいかねません。
回復も同じで、モメンタムが大事です。飲み友だちと一緒に飲み屋に行き、自分はソフトドリンクを飲んでいれば淋しくはないかもしれません。けれど、飲み屋には「酒を飲むことは良いことだ」というモメンタムがあり、人はしばしばそれに巻き込まれて、酒を飲めない自分を惨めに感じてしまいます。一方でAAミーティングには(断酒会の例会にも)「酒を飲まないことは素晴らしいこどだ」という、飲まない方向へと人を押すモメンタムがあります。何ごとであれ、成功するためには「良い流れ」を引き寄せなければなりません。AAミーティングには回復したい人にとって望ましいモメンタムがあるのです。
けれどAAは、「AAミーティングはAAグループの行う主要な活動だ」と述べているものの、個人が回復するための主要な手段である、とは決して言いません。なぜでしょうか?
「AAミーティングに出続けることで断酒が続けられる」と感じているAAメンバーは少なくありません。そう感じている人の中では、
という図式が成り立っています。努力が実を結ぶという実に分かりやすい因果関係です。けれど、努力することで酒がやめられるのならば、私たちは「アルコールに対して無力」ではなくなり、アルコホリズムという病気は私たちの意志の力で解決可能な問題になってしまいます。それはステップ1と矛盾します。
つまり、AAミーティングに参加することは、酒を止めることの「役には立つ」けれど、AAミーティングはアルコホリズムの最終的な解決手段ではないということをステップ1は教えてくれるのです。
AAミーティングには人間の精神を変えてくれる力があることは多くの人が認めています。はたしてその変化は、「アルコホリズムからの回復をもたらすに十分なほどの人格の変化」(BB, p.266/570)なのでしょうか?
ミーティングメイカーとステップテイカー
AAミーティングによって十分な変化が起こると信じている人たちはミーティングメイカー(meeting maker)と呼ばれます。彼らは実質的にはステップ1の「アルコールに対する無力」を認めていません。なぜならミーティングに参加するという「人間的な努力」によってアルコホリズムが解決できると考えているからです。その代わりに彼らはミーティングを大事にし、アルコホーリクが助かるために必要なAAミーティングを増やしていくことの重要性を強調します。それゆえに彼らはミーティングメイカーと呼ばれるのでしょう。ミーティングメイカーのなかにも12ステップに取り組む人はいますが、それは「酒をやめるため」ではなく――なぜなら酒をやめるのにはミーティングがあれば十分なのですから――「より良く生きるため」などのような断酒以外の目的であることが多いようです。彼らの合い言葉は「仲間のおかげ」です。
AAミーティングの効果を認めつつも、それに参加するだけでは十分な変化は起こらない、と考えている人たちは、やがて変化の道具としての12ステップにたどり着き、ステップテイカー(step taker)になります。彼らは人間的な力(意志の力やミーティングの効果)の限界を認めているので、ステップ1の無力を認めることができ、ステップ2へと進んでいけます。ステップテイカーにとってみれば、アルコホリズムの解決はハイヤーパワーがもたらしてくれるもので、AAミーティングは解決を伝えるための手段にすぎません。
AAメンバーは、ミーティングメイカーになるか、あるいはステップテイカーになるか、それともどちらにもなれないかの三択です。
ではなぜステップテイカーはミーティングだけでは十分な変化が得られないと考えているのでしょうか?
自分をごまかしているだけではないのか
その答えはビッグブックの第十一章の冒頭にあります。その文章は、酒を飲むことの素晴らしさを称える文章から始まります:
飲むこととは、和気あいあいと陽気におしゃべりをし、想像力を膨らませることを意味する。心配ごと、退屈さ、悩みなどの憂さを晴らし、友人たちと打ち解けた楽しい時間を過ごすことであり、生きている素晴らしさを実感することである。5)
だが私たちは、アルコホリズムという病気によって、その「生きている素晴らしさを実感する」という行為を禁じられてしまいました。それは大きな喪失でした。次のページにこうあります:
かなりの大酒飲みが、たまたまいまは飲んでいないと、よくこんなことを口にする。「飲んでいたころがなつかしいなんて、ぜんぜん思わない。やめたほうが気持ちはずっと楽だし、仕事もはかどる。ともかくいまのほうがはるかにいいね」。
かつての問題飲酒者である私たちは、こうした飛び上がった発言を耳にすると、にんまりしてしまう。落ち込まないように、暗闇のなかで口笛を吹いている少年みたいにその人が振る舞っているだけなのを、私たちはよく知っているからだ。彼は自分をごまかしているので、内心では、酒を半ダース飲んでも何ごともなく切り抜けられるようになるためになら、どんなことだってしようと思っているのだ。6)
そう、確かに飲酒から解放されたのは素晴らしいことです。その喜びを表現することは大切です。けれど、私たちの深いところでは――飲酒欲求などという表面的な欲望ではなく、もっと深いところで――「昔のようなやり方で人生を楽しみたいというあこがれ」が、いつまでも居座り続けているものなのです。
回復するためには自分に正直にならなければなりません。「もう酒への欲求は断ち切れた」などと自分をごまかしていては回復は望めません。
ミーティングには確かに効果があります。その効果を信じ、実感することも大切ですが、同時にミーティングの効果の限界も認めなければなりません。ミーティングだけでは自分はまだ病気に支配されたままで、救われないのだ、と認めることなしにステップ1は実践できません。だからこそAAは、ミーティングが個人が回復するための主要な手段だと言うことを避けているのです。
このように、酒をやめるのに、自分の意志の力も役に立ちますし、AAミーティングも役に立ちます。その効果を信じれば信じるほど、ステップ1の無力を認めることができなくなってしまいます。必要なのは、自分の意志の力にも、AAミーティングの効果にも限界があることを認めることです。その限界を超えた先では、意志の力もAAミーティングも役に立たない・・・それがアルコホーリクの置かれた現実です。
意志の力もミーティングも(ある程度)役に立つからこそ、ステップ1が認めづらくなる、というのは皮肉なことです。
二番底(本当の底つき)
先ほどの続きです:
彼には、アルコール無しの人生なんて考えられない。そしてやがてはアルコールの有る無しにかかわりなく、人生そのものについて考えられなくなってしまうだろう。そのとき彼は、誰も知ることのないような孤独を味わう。彼はまさにぎりぎりのところにいる。終止符が打たれるのを心から待ち望むようになる。7)
酒を飲めば辛いことが起きることはわかっています。けれど、酒を飲まないで生きている現在も辛いのです。なぜなら、酒(あるは薬物)には苦しみを癒やしてくれる効果があるのに、自分がアルコホーリクだと認めた以上、酒には手を出せなくなったからです。病気ゆえに酒に手を出してしまう自分を正当化することもできなくなっています。そうやって癒しのないしらふの生活を続けていくと、辛さが次第に積み増しされていき、それがしばしば耐え難いレベルに達するのです。
それでも酒の世界には戻れません。かといってしらふの人生も辛い・・・。どうしたら良いのかわからない板挟みの状況に置かれているのが、そのような状態に至った人たちの非常に厳しい現実なのです。
これを本当の底つきと呼ぶ人たちもいます。アルコホーリクは酒を飲みながら「底をつく」ことで断酒を始めますが、本当の底つきは酒をやめた後に、かなり時間が経過してからやってきます。二回目の底つきなので「二番底」などと呼んだりします。
ビッグブックに書かれているとおり、この板挟みの状況に置かれ、酒を飲むこともできず、かといってしらふで生きることもできず、自ら死を選んでいった人たちも少なくありません。僕が12ステップについて学び始めたのも、板挟みの中で自ら死を選んだスポンシーがいたからでした(何よりも自分が救われたかったからでもありますが)。
自分の意志の力とミーティングだけでは、この板挟み状況から抜け出すことはできません。少なくともステップテイカーたちはそう考えています。アルコホーリクが本当に救われるためには、人間の努力を越えた力が必要なのです。そのことを納得するのに、この二番底が最適のタイミングだと言えます。
人と違ってしまう
もう一つ、ステップ1の無力を認めることが難しいのは、それを認めると私たちは「普通の人」ではなくなってしまうからです。しばしばAAミーティングで読まれる第三章の冒頭にこうあります。
私たちのほとんどは、自分が本物のアルコホーリクだとは認めたがらなかった。自分の肉体や精神が、まわりにいる人たちとは違うなどということを、喜んで認める人間がいるわけはない。8)
ステップ1の無力を認めることは、自分が周囲の人たち(つまり、普通の、健常な人たち)とは違う種類の人間になったということを受け入れることです。
普通じゃないと言っても、単に飲酒がコントロールできないというだけのことなのですが、他の人たちが当然のようにできることが「自分にはできない」と認めるのは、本人にとってはかなりの恥辱であったりするのです。だから否認というのも起きうるし、「普通の人になること」を回復の目標に据えてしまう人たちもいます(そんなの無理なのに)。そうでなくても、「アルコホリズムになったことで、普通の人より良い生き方が手に入った」などと強がりを言って見せたりする回復者(笑)も少なくありません(数年経ってさらにしらふになると、恥ずかしくなって、そんなことは言わなくなるのが通例ですが)。
酒をやめたとしても、回復できたとしても、アルコホーリクは一生アルコホーリクのままです。だが、そのことがなかなか受け入れられないのが人間というものなのでしょう。
同じことはAA以外のステップにも当てはまります。アディクトは回復できてもアディクトのままです。ACは一生AC(共依存)のままです。ACの共同体の人の話によると、多くのACは「ACではない人生を手に入れたい」と願っているものなのだそうです。それが実現できると考えている時点で、もう自分がACであることを否認しているようなものなのですが、そのことには気づかないのです。
回復が進んでいけば酒や薬はとまり、そうすれば人々は(私たちが自ら明かさない限り)私たちがアル中やヤク中だとは気づかなくなるでしょう。ACの場合も回復が進んでいけば共依存行動も減っていき、ACっぽさも少なくなるでしょう。けれど、私たちのなかの病気は消えてなくなりはしません。私たちは一生普通の人とは違ったままなのです。ステップ1はその現実を受け入れ、認めるステップです。
かように、ステップ1の無力を認めることは困難なことなのです。
今回からステップ2に入る予定だったのですが、ステップ1から2への橋渡しの文章を書くつもりで、ステップ1の振り返りだけになってしまいました。次回こそステップ2に入ります。
今回のまとめ
- ステップ1では、自分の抱えている病気のせいで自分の人生や生活がダメージを受けているのに、それを自分では解決できないことを認める。
- 意志の力(自制心)やAAミーティングに参加することは、(ある程度は)酒をやめることの役に立つ。
- 役に立つからこそ、意志の力やミーティングの効果を信じ過ぎてしまい、それらにも限界があることを認めるのが難しくなる。
- 私たちは病気を抱えたことによって、普通の人たちとは違う種類の人間になったのであり、それは一生変わらない。それは認めづらい真実である。
- BB, pp. xx (20), xxv (25), 29-30.[↩]
- SLAAは「セックスと恋愛/愛情のアディクション(sex and love addiction)」、SAAとSRAは「性嗜癖(sex addiction)」、SAは「セクサホリズム(sexaholism)」、SCAは「性強迫症(sexual compulsion)」。[↩]
- AA(AA日本出版局訳編)『どうやって飲まないでいるか』, AA日本ゼネラルサービス, 1979, p.12.[↩]
- op. cit., pp.162-176.[↩]
- BB, p.219.[↩]
- BB, p.220.[↩]
- BB, pp. 220-221.[↩]
- BB, p.45.[↩]
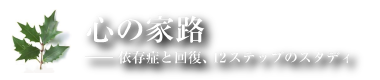
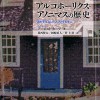



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません