ビッグブックのスタディ (15) 医師の意見 6
ここからは精神の問題について
第12回と第14回では、アルコホリズムの身体の問題を説明しました。アルコホーリクが飲酒をコントロールできないのは、アレルギー反応(渇望)という身体的な現象が原因だ、という説明でした。
しかしながら、最初の一杯を飲むこと――スリップが起こる原因は、アレルギー反応では説明できません。今回は、精神の問題の話を始めます。
アルコールは「気分を変える薬」
xxxvi (36) xxxix (39)ページの先頭から:
人は本質的に、アルコールがもたらす酔いの効果が好きで飲む。1)
人が酒を飲むのはアルコールのもたらしてくれる「効果」が好きだからです。それは気分を変える効果です。
アルコール以外にも依存症をもたらす薬物はたくさんあります。覚醒剤 ・麻薬 ・大麻 ・ベンゾジアゼピン など、どれも気分を変える効果のある薬です。アルコールを含めこうした薬物を英語でmood altering drug(=気分を変える薬)と呼びます。また最近ではギャンブル・ネットゲーム・買い物・浪費・性行動なども依存症と呼ばれるようになってきましたが、これらの行動にも気分を変える効果があります。摂食障害の人によると、過食や嘔吐にも気分を良い方向に変える効果があるのだそうです。
つまり、アディクションの対象となるものは、気分を変える効果があるものに限られるのです(気分を変える効果のないものへのアディクションはあり得ない)。しかもある程度大きな効果がすぐに得られなければなりません。例えば、アトモキセチン (商品名ストラテラ)というADHDの薬は、気分を変える効果が大きくないので、ストラテラの依存症になったという話は聞きません。
そして、アルコールは日本中どこでも、合法的かつ安価に、面倒な手続きなしに、人目を憚かることなく入手可能な「気分を変える薬」であり、愛用者がとても多いのです。
日本酒造組合中央会 が2017年に行った調査では、日本人の成人の飲酒率は42.7%でした。2) そして、第9回で取り上げたようにアルコール依存症の有病率は1.1%です。飲酒者のうち依存症になるのは約40人に一人にすぎず、大多数の飲酒者はアルコールを「気分を変える薬」として使いながら無事に過ごしています。
対処の手段としての酒
人は誰でも気分を変えたくなることがあります。例えば、仕事で失敗して上司に怒られたことで、明日仕事に行くのが嫌になることもあるでしょう。家族と喧嘩して家を飛び出せば、戻って家族と顔を合わせるのが気まずく感じられるでしょう。そんな時に酒を飲めば、気分が変わり、明日も仕事に行こうとか、家に戻ろうと考え直すことができます。あるいはなんらかの事情で未来に希望が持てず生きる気力が失われたとき、酒で気分を変えることで気を取り直して生きている人も多くいることでしょう。
アルコールは心理社会的ストレッサー によって引き起こされた感情的問題への手軽な対処ツールとして多くの人に活用されているのです。習慣的飲酒者の多くは、人生を歩むための杖として酒に頼っています(依存という意味ではない)。そして、その大多数は、アルコールへのアレルギー体質を持たないので、渇望が起きることなく、無難な飲酒を続けています。
ところが本人の意志とは関係なく、ある体質を持って生まれたために、酒を飲むと渇望が起きてしまい酒量をコントロールできなくなる人たちがいます。そのような状態になるとアルコール依存症という病名が与えられ、「酒を飲んではいけない」と言い渡されてしまうのです。本人たちにしてみれば、これまで最も頼りにしてきた対処手段が使えなくなるのですから、これは生きる上での大きな危機です。
アルコホーリクは、対処手段として酒ばっかり使ってきたので、それを奪われてしまうと、コーピング能力が大きく下がるという特徴があります。他の手段が上手く使えないがために、使い慣れた酒に戻っていってしまいます。
もっと別の健康的な手段を使えば良いではないか、と思われるかもしれません。ごもっともな意見です。例えばスポーツで健康的な汗を流すとか、お茶を飲むとか、友達と電話で話すとか、いろいろ手段が考えられます。AAの『どうやって飲まないでいるか』という書籍はいろいろなコーピングスキルを紹介していますし、SMARPP も薬物再使用の危機的な状況に対処するスキルを身に付けるプログラムになっています。
そのように他のコーピングスキルを身に付けることは必要であるし、有効な手段であることも確かなのですが、AAやNAのなかではそれが回復の本質だとは見なされていません。それはなぜでしょうか。
酒が一番自分と相性が良い
ノン・アルコホーリクの人に「ストレスが溜まったときに、どうやって解消されてますか?」と聞いてみると、その答えは人さまざまです。スポーツジムで身体を動かす人もいれば、カラオケという人もいるし、甘いものを食べるという人もいます。では、なぜそれを選んだのかと聞けば、「それが一番自分にあっているから」という答えが帰ってくることが多いです。
上に述べたように、人は誰でも生きるなかで感情的な問題をしばしば抱えます。そしてそれに対処しようと(つまり気分を変えようと)様々な手段を試してみるものです。多くの人は、子供から大人になる過程のどこかで、自分と一番相性の良い手段を見つけ出します。それは一番効率よく気分を変えてくれる手段です。ある人にとってはそれはスポーツジムであり、別の人にとってはカラオケなのでしょう。
そして、僕にとってはアルコールが最も「自分に合った」手段でした。酒を飲むとちっぽけな自分が大きくなった気がしましたし、口下手な自分が気さくに人と話せるようになれた気がしました(実際には酔ってくだを巻いていただけでしょうが)。酒は素晴らしいものだと思いました。(cf. E・M・ジェリネク『アルコール中毒という病気』の「始まり」の項)
僕は一度だけパチンコをやったことがありますが、パチンコのどこが面白いのかさっぱり分かりませんでした。気分の変化もありませんでした。しかし、知り合いのギャンブラーの人に聞いたところ、彼が最初にパチンコをやったときには「これだ! こんなに素晴らしいものは他にはない」と思ったそうです。ところが彼は酒にはそれほど魅力は感じないようでした。
人生を生きる中で、人は自分と相性の良いコーピング手段を選び取ります。そしてそれを使って感情的問題を乗り越えることを憶えます。それは、まるで最愛の恋人(あるいは最高の友人)のような存在であり、それが見つかったということは人生における幸せの一つでしょう(渇望さえ起きなければ)。そういう存在に出会えない人生は(依存症になるリスクはないかもしれないが)、ずいぶん味気ないのではないかと思うのです。
そのベスト・パートナーとの蜜月がずっと続けば良いのですが、アルコホーリクの場合には、アレルギー体質を持っているがために、アルコールと別れざるを得なくなります。どういう体質に生まれるかは自分では選べないのですから、これは不運としか言いようがありません。他の相手を探そうにも、アルコールさんほど相性の良い恋人はなかなか見つかりません。だから、またアルコールとヨリを戻してしまうのです。
強迫観念
「断酒中のアルコホーリクが、感情的問題を解決するために再飲酒する」なんて信じられないかも知れません。飲んではいけないことを知っているし、飲んだらどうなるかも分かっているのに、なぜアルコホーリクは再飲酒してしまうのでしょうか。それまでは自分の意志でやめ続けていた、と周囲は理解していますから、当然再飲酒も自分の意志で行ったと理解します。周囲の人にしてみれば「アルコホーリクが断酒の決意を翻して、酒を飲んだ」という捉え方しかできず、裏切られた気分になります。
実は、再飲酒(スリップ)するときのアルコホーリクの頭の中では、奇妙な精神的現象(BB, p.55)が起きています。飲んではいけないという理性的で健全な考えと同時に、最初の一杯を飲むことを正当化する狂った考えが並行して存在しているのです。この狂気の考えは通奏低音 のように、明確に意識されなくても常にアルコホーリクの意識の底に存在していて、感情的な危機の際に表面に現れては、健全な考えを打ち負かし、アルコホーリクの行動を支配し、酒を飲ませてしまいます。
この現象をAAでは強迫観念(obsession)と呼んでいます。強迫性障害 という病気にも強迫観念がありますが、相通じるところがあります。例えば強迫性障害のひとつである不潔恐怖は、手の汚れが気になって、何度も何度も手を洗わないと気がすまなくなります。この「手が汚れている」という考えが強迫観念であり、繰り返し手を洗う行為は周囲には理解不能です。そして本人もこうした症状に思い悩んでいます。
アルコホーリクの場合には、最初の一杯を飲むことを正当化する考えが強迫観念であり、それが健全な考えに打ち勝って飲んでしまう行為は周囲には理解不能です。そして本人も再飲酒したことを思い悩むのです。
強迫観念というアルコホリズムの精神的症状が、再飲酒という結果を引き起こしているのです。スリップする瞬間、その人は狂気に支配されています。再飲酒は、「油断したから」とか「気が緩んだ」とか「本気度が足りなかった」という言葉で表現されることが多いのですが、それはこの狂気の存在を認めず、自分の精神が再飲酒の瞬間も健全に機能しているという立場に立ちたいがための虚しい言い訳にすぎません。
強迫観念には勝てない
続きです:
その感覚は実につかまえどころがなく、危険であると思っても、やがてその判断の真偽がつかなくなっていく。1)
危険だと分かっていても最初の一杯は防げません。なぜならそれを飲むときアルコホーリクの頭は強迫観念に支配されているからです。
生きている限り、感情的な危機は避けて通れません。少々の危機であれば他の手段を使って乗り越えることもできるでしょうし、そうしたスキルを身に付けることは役に立ちます。しかしそうした手段によって対処できる範囲を超えて、強迫観念がむくむくと大きくなってきたとき、私たちアルコホーリクの精神はそれに対処する術を持ちません。「防御を固めていても、それはある日、酒を一杯飲むための取るに足らない言い訳の前に崩れ去る」(BB, p.61)というのが嫌な現実です。
今回の話はジョー・マキュー(Joe McQ, 1928-2007)とチャーリー・P(Charlie P., 1929-2011)による The Big Book Comes Alive の強迫観念の説明をベースにしました。3)
この先、ビッグブックの第一章、第二章、第三章と、強迫観念のことが繰り返し取り上げられていきます。なぜそんなにしつこく書かれているのかと言えば、それだけ大事なことであるし、またそれだけ認めづらいことだからでもあります。
- アルコールには気分を変える効果がある(アディクションの対象になるものには、すべて気分を変える効果がある)。
- 社会の中で多くの人が、心理社会的ストレッサーによって引き起こされた感情的問題に対処するために、アルコールという薬を使っている。
- そのなかにアルコールに対するアレルギー体質を持つ人だけがアルコホーリクになる。
- 感情的問題に対してアルコール以外の対処手段を身に付けるのは断酒の役に立つ。
- しかしその人にとってアルコールが最も相性の良い手段である以上、他の手段では不十分なときもある。
- 再飲酒(スリップ)するときのアルコホーリクの頭の中では強迫観念(obsession)が起きており、最初の一杯を飲ませる狂った考えが、飲んではならないという健全な考えに打ち勝ってしまう。
- 強迫観念というアルコホリズムの精神的な症状が、再飲酒という結果を引き起こしている。
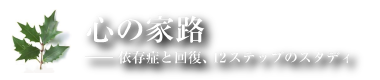
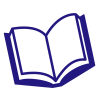


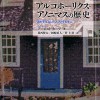
最近のコメント