12ステップのスタディ (21) ステップ1全般 (1)
各共同体の創始の歴史の説明が一巡したので、ステップ1の説明に移ることにしましょう。
この連載は、各共同体の12ステップに共通しているところ(共通点)と、違っているところ(相違点)を明らかにすることを狙っていますので、まずは共通している点を説明してから、各共同体のステップの説明に入るのが良いでしょう。
オブセッションとコンパルジョン

最初に取り上げるのは obsessive-compulsive(オブセッシブ・コンパルシブ)という概念です。これは、アディクションを obsession(オブセッション・強迫観念)と compulsion(コンパルジョン・強迫行為)の組み合わせとして理解する考え方です。
これはAAの12ステップで、アルコホリズムを強迫観念(obsession)と渇望(craving・クレービング)の組み合わせとして説明したのが始まりです。NAはAAの疾病概念や回復の手法をそのまま受け継ぎましたが、NA共同体をAAから独立させるために、AAとは違った用語のセットを採用しました(第5回)。その時に、渇望という言葉を compulsion という言葉で置き換えました。
↓
もとよりクレービング(渇望)は多義的で誤解を生みやすい言葉だったのに対し、コンパルジョンという言葉は意味が明確でした。NA以降の共同体でもっぱらコンパルジョンが使われるようになったのは、おそらくそれが理由なのでしょう。
そしてNA以降に成立した共同体では、自分たちをコンバルシブ・オーバーイーター(OA)、コンパルシブ・ギャンブラー(GA)、セクシャル・コンパルシブ(SCA)などと呼ぶようになりました。それぞれ、強迫的オーバーイーター、強迫的ギャンブラー、性的強迫症者と訳されています。
さらに驚くべきことに、この obsessive-compulsive という概念は、共依存の分野、すなわちアダルトチルドレン(AC)の共同体でも採用されているのです。
というわけで、この obsessive-compulsive は多くの共同体のステップ1に共通する概念であり、そのもとはAAのビッグブックに記述された「精神の強迫観念と身体的渇望」なのです。
それゆえに、この obsessive-compulsive あるいは「オブセッションとコンパルジョン」と表現される概念を理解せずしてステップ1の「無力」を語ることはできません。これはそれほどまでに重要な概念です。
ただし例外もあることを申し添えておかなければなりません。アラノンなどの家族グループと、感情の問題を扱うエモーションズ・アノニマス(EA)ではオブセッションとコンパルジョンとは異なった疾病概念を用いています。
強迫性障害という病気
英語の病名に詳しい人は obsessive-compulsive という言葉から、強迫性障害 (obsessive-compulsive disorder、OCD)という病名をすぐに思いつくでしょう。これはかつて強迫神経症と呼ばれていた病気で、将来は強迫症と呼ばれるようになりそうです。
様々な12ステップ共同体が obsessive-compulsive という概念を使う理由は、彼らの嗜癖と強迫性障害との間には「ある程度の」類似性があると考えているからです。
あらかじめ申し上げておきますが、これは嗜癖(依存症)は強迫性障害の一種であるという主張ではありません。両者にある程度の類似性があることを主張するのみで、同じ病気だと捉えているわけではありません。また、この話をするとほぼ決まって「強迫性障害の人は依存症になりやすい」という話題を持ち出す人がいますが、そのような脱線を望んでいるわけでもありません(そもそもDSM-IVでも、DSM-5でも、強迫性障害の併発症の中に物質使用障害は挙げられていません)。1) 2) その点をご理解頂いた上で、以下を読み進めて頂ければ幸いです。

まず強迫性障害(OCD)とはどんな病気かを説明しなければなりません。それは文字通り obsession(オブセッション)と compulsion(コンパルジョン)を特徴とする病気です。
obsession は強迫観念と訳されます。強迫観念は何らかの観念(idea)・考え(thought)・衝動(impulse)・イメージ(image)で、本人にとって不適切で煩わしいものです。例を挙げれば、手が汚れている、部屋の鍵をかけ忘れた、食器がいつもの順番で棚に収まっていないと子供が交通事故に遭う、静かな集会でわいせつな言葉を叫んでしまう、ポルノ画像が脳裏に浮かんで消えないなどです。そしてそのことが、本人に強い不安や苦痛をもたらします。
compulsion は、強迫行為や強迫衝動、時には制縛と訳されます。これは強迫観念を中和するために取る行動です。例えば、手が汚れているという強迫観念を中和するために手を洗う、鍵のかけ忘れを確かめに帰る、食器の収納の順番を念入りに確認する、猥雑な言葉やイメージが浮かばないように心の中でひたすら数を数える、などです。
特徴的なのは、強迫観念も強迫行為も反復されることです。つまり繰り返しそれが生じます。その結果として、手を洗いすぎて皮が剥ける、数分おきに鍵の確認に戻るので出かけられない、繰り返し収納の順を確かめたり、頭の中で数を数え続けるので他のことができないといった、生活上・職業上のトラブルが引き起こされます。
もう一つの特徴は侵入性(intrusiveness)です。これは「無理強い」という意味です。本人はどこかの時点で、自分の思考や行動が非現実的で不合理だということを認識しています。手は汚れていないから洗う必要も無い。鍵がかかっていることはさっき確認したし、食器の並び順と子供の事故は無関係だし、今まで一度も教会のミサで叫びだしたことはないから心配はいらないと分っています。しかし、強迫観念は強い不安や苦痛をもたらすために、それを中和するために強迫行為をせざるを得ないのです。
つまり、強迫性障害の人は、本人が望んでいない思考や行為を病気によって強制され、繰り返し不合理な行動を取った挙げ句、本人が最も不利益を被り、時には周囲にも迷惑を掛けているのです。
そして、この病気が長期化すると、強迫行為によって強迫観念を中和しようという抵抗を諦めてしまうこともあります。他人が触ったドアノブに触ると手が汚れるという強迫観念に抵抗できなくなると、まったく外出しないで自宅に引きこもることしかできなくなります。
アディクションも、意志に反した思考と行動を病気に強制される
そして、アディクションも強迫性障害と同じくオブセッションとコンパルジョンの組み合わせの病気だ、と12ステップ共同体では考えているのです。もちろん、オブセッションとコンパルジョンの内容は強迫性障害と(ある程度共通性はあるものの)同じではありません(詳しくは各共同体のステップ1で解説します)。しかし、「本人が望んでいない思考や行為を病気によって強制され、繰り返し不合理な行動を取った挙げ句、本人が最も不利益を被り、周囲にも迷惑を掛ける」という点は、強迫性障害とそっくりなのです。
先ほど、家族グループやEAではオブセッションとコンパルジョンとは異なった疾病概念を用いていると述べましたが、これらの共同体でも自分たちの問題をある種の病気として捉え、その病気によって望まない思考と行動を強制されている、という考え方を採用している点は共通しています。

アディクションという病気はまだ十分解明されているとは言いがたいのですが、治療の現場からはいくつかの仮説が出てきています。例を挙げるなら自己治療仮説や、信頼障害仮説です。自己治療仮説はカンツィアン(Edward Khantzian, 1935-)らが唱えたもので、著書『人はなぜ依存症になるのか 自己治療としてのアディクション』3)によって日本に紹介されました。これは、人は自分が抱える苦痛に対して酒や薬を自己投薬することで嗜癖に陥っていくという主張です。また信頼障害仮説は小林桜児医師が著書『人を信じられない病 信頼障害としてのアディクション』4)で唱えたもので、幼児期の逆境体験などにより他者との信頼関係を結べなくなることが嗜癖を引き起こす要因の一つだと主張するものです。

それらのその内容についてはここでは詳しく触れないので、関心のある人は参照書を読んでいただきたいのですが、どちらも依存症者は快楽主義なのだとか、不道徳なのだという社会の見方を覆すために提唱されたものです。そして、それらの内容は、12ステップグループの文化と特に衝突するようなものではありません。
カンツィアンの本が翻訳出版されたのが2013年、小林医師の本の出版は2016年ですが、それらの出版以後のおよそ10年間に、この二つの仮説が元の主張とは異なる方向へ恣意的に解釈される傾向が強まっていることが大変気にかかります。
恣意的というのは、この二つの仮説が、アディクションの人が酒や薬を使っているのは「ある程度は本人の自由な選択の結果である」という理解の根拠にされるようになったことです。その理解にもとづいて、その人を取り囲む環境や関係性を変えれば、酒や薬を使わないという選択をさせることができる、という理論が組み立てられています。その根拠としてしばしば持ち出されるのがラットパーク実験 です。
そこで見落とされているのは、嗜癖(依存症)は一次疾患であるという事実です。その人がアディクションになったのは、苦痛に対する自己投薬や信頼障害が要因の一つとして働いたのかもしれません(他の理由かも知れません)。しかし、どんな理由であれ、いったんアディクションになってしまえば、アディクションは単独で存在し、アディクションになった理由を解決しても、アディクションそのものは疾患として残り続けるのです。
もとより二つの仮説は、社会に存在する、アディクションは本人の自由な選択の結果であり、自業自得なのだという偏見を払拭するために提唱されたものであるにもかかわらず、むしろその偏見を強めるように利用されてしまっているのが現状です。
必要な視点は、嗜癖というものは、いったんこの病気になれば、本人の自由な意志に反して、繰り返し(飲酒や薬物使用という)不合理な行動を強制されてしまうものなのです。そこに本人の苦しみがあります。その段階に至れば、なぜ嗜癖になったのかはもはや関係ありません。
アディクションは心理的問題ではなく病気なのだということを再度ここで強調しておきます。
弄便(ろうべん)とは認知症の症状の一つで、おむつのなかの大便を素手で触ったり、その便を衣服やベッドの手すりや壁などになすりつけたりする行為です。例えその人が弄便の最中に微笑みを浮かべていたとしても、「この人はスカトロ趣味で、この行為から快楽を得ているのだ」とは考えないでしょう。認知症という精神疾患ゆえに、そのような行為に及んでいるだけで、自由意志によるものと捉えるべきではありません。
また、弄便を解決するためには「なぜこの人は認知症になったか」という理由はあまり意味がありません。ひょとしたらその人は孤独で、人との関わりが少なかったから認知機能の低下が進行したのかもしれません。だとしても、その人の孤独を取り除けば弄便が収まるというものでもありません。むしろ、なるべくトイレで排便するとか、おむつをこまめに交換するなどの(認知機能をあてにしない)「別の対策」が効果を示すのです。
弄便は看護・介護する人にとっては大きな精神的負担になります。だが弄便を「本人の意志で行われている行為」だと捉えてしまえば、ますます腹が立ちストレスが増えるだけです。弄便は認知症の症状で、本人が望んで行っていることではない、という理解が必要です。

僕はアウトリーチ活動には熱心ではありませんが、僕が若かった頃に交流のあった断酒会の人たちは、飲んでいる人を訪問する活動を行っており、その状況を聞かされていました。アル中の最期はどれもよく似ていて、肝肥大と腹水 によって腹がカエルのように膨れあがり、猛烈なけん怠感でなかなか動けず、それでも酒を飲み続けています。しかし彼らの口から出てくるのは「もう酒は飲みたくない」という言葉なのです。しかしその「飲みたくない」という意志に反して、彼らは泣きながら酒を飲んで死んでいくのです。その行為を止めさせるには入院させるしかありませんが、退院すればまたこの状況に戻ってしまいます。だから病院の側からは治療しても無駄な、迷惑な患者だと見なされてしまうのです。
これはアルコホリズムの末期の状態ですが、私たちはそこに向かって自由な意志を徐々に病気によって奪われていくのです。
問題は自分の中にある
オブセッションとコンパルジョンは、病気によって私たちの自由な意志がどのように奪われ、望まない思考と行動を強いられるかを説明してくれる概念です。
人は自分が狂っているとは考えたくありませんし、自分は正気だと信じたいものです。だから、せっかく断っていた酒を飲み始めてしまったのも、あるいはトラブルを起こすほど飲み過ぎてしまったのも(愚かな選択だったかもしれないが)自分の自由な選択の結果だと思いたいのです。
あるいは、酒を飲んだのも、飲み過ぎたのも、周りの環境が悪いからであるという理由付けを行うこともあります。
しかし、このオブセッションとコンパルジョンという概念は、スリップしたのも、飲み過ぎたのも、自由な選択の結果ではなく、もちろん自分を取り巻く環境のせいでもなく、自分の中にあるアディクションという病気ゆえなのだ、と教えてくれるのです。
この病気になった原因は、環境の中にあるかもしれず、幼児期の逆境体験にあるかもしれず、信頼できる関係がなかったからかもしれません・・・しかし、12ステップ共同体は人がなぜアディクションになったかには関心を持ちませし、それを探ろうともしません。関心を持つのは、それをどうやって解決するかです。[BBS#53]
その解決のために、自分の中にあるアディクションに着目していくのがステップ1です。そして、その自分の中にある病気に焦点を当てるという手法は、OAやGAやSAなどにも受け継がれました。
さらにそれは、アダルトチルドレン(AC)の共同体にも受け継がれています。ACがACになった原因は親の養育にあります。ACの文化においては、自分の身に起きた悪いことはすべて親の子育てが悪かったからという原因に求めるのがお作法です。傍から見ていると、「いや遺伝の問題とか、家庭以外の環境の問題とかあるでしょ?」とツッコミを入れたくなりますが、それは余計なお節介というものであり、ACの文化においては「すべては親のせい」で良いのです。しかし、ACはすでに大人になってしまっている以上、現在の問題は親の中にあるのでもなく、自分を取り巻く環境にあるのでもなく、自分自身の中にある、という理解をACのステップ1は提供します。そして、その理解を助けるためにオブセッションとコンパルジョンという概念がここでも使われているのです。
学習性無力感という問題
アルコホーリクが本人の意志に反した飲酒を病気に強制されているにしても、それに抵抗しようともせずに、飲み続けていることはよくあります。つまり「酒をやめたい」とか「もう飲みたくない」という意志が表明されずに、「飲みたいから飲んでいるのだ」という態度でいるのです。
「うちの旦那の酒が止まるわけがありません。だって、本人にやめる気が無いんだから」とおっしゃる奥様はたくさんいます。それは旦那さんの言葉を、言葉通りに受け取って「酒をやめる気が無い」と判断しているのです。
AAではメンバーが精神病院を訪問して、そこに入院しているアル中患者と話をする活動を行っています。近年は病院の管理上の都合から、患者さんと個別に面会して話をすることはできなくなっていて、病院の治療プログラムの一環として患者さんを一室に集め、そこでAAメンバーが話をする形式になっています。AAメンバーだけでなく患者さん側も話をしてくれることもあります。この時、病院のスタッフ(看護師とかソーシャルワーカー)が同席している場合と、同席していない場合とで、患者さんたちの言うことが異なります。
スタッフが同席している場合には、「私もAAの皆さんを見習って、退院したらきっぱり酒をやめようと思います」などと模範的な発言が目立ちます。これは刑務所で刑務官が同席している場合も同じです。
スタッフがいない場合には、かなり高い確率で本音を語ってくれます。例えば、AAのメンバーに対して「酒をやめているとおっしゃいましたが、本当は今日この帰りに飲むんじゃありませんか? 今日飲まなかったとしても、年に何回かは飲んでるんじゃありませんか?」などと、AAメンバーが酒を完全に断っていることを信じず、疑いを差し挟むのです。または、「皆さんは立派に酒をやめられているかもしれないが、私には無理だ。私には酒はやめられない」とおっしゃる人もいます。治療を行っているスタッフからすれば、どちらも好ましくない発言と捉えられてしまうので、スタッフ同席の場合にはこうした本音はまず聞かれません。
ではなぜ彼らは、断酒している人の存在を信じず、また自分には断酒は無理だと考えるのでしょうか? それは経験者なら簡単に分ります。酒をやめる努力を何度もしたのに、そのたびに再飲酒という失敗を繰り返したので、自分には無理だという結論が引き出されてしまったのです。
人は長期にわたって苦痛にさらされ、しかもその苦痛を回避したり抵抗したりできない状況に置かれると、その状況から逃れる努力をやめてしまいます。この現象を学習性無力感 と呼びます。依存症は「否認の病気」と呼ばれますが、本人が問題の存在を否定していると捉えるのは、その発言を言葉通り受け取りすぎなのです。むしろ、問題の存在を十分に意識し、その解決を図り、しかも解決に繰り返し失敗した挙げ句、これはどんな努力をしても解決不能だという学習性無力感を獲得してしまっているのです。
飲酒や薬物使用によって人は快楽を得ますが、過剰な飲酒や薬物使用は得られる快楽以上に大きな苦痛をもたらします。その点は、ギャンブルや過食嘔吐などでも同じです。誰しも苦痛からは逃れたいと思うものです。しかし、オブセッションがあるためにその苦痛から逃れることはできません。強迫性障害の場合にオブセッションへの抵抗をやめてしまう人たちがいると述べましたが、アディクションの場合にはオブセッションへの抵抗をやめてしまう人がほとんどだと言っても過言ではありません。
学習性無力感への対策

ではどのようにしたらこの学習性無力感を解消することができるのでしょうか? 学習性無力感に対する一般的な対策はともかく、AAなどの12ステップグループが採用している手法はシンプルです。それは、同じ問題を解決した人たちと一緒に過ごすことです。AAの創始者ビル・Wは、旧友であり自分より酷いアル中だと思っていたエビーと話をし、エビーが酒をやめている姿を見て、「自分にもできる」と信じるようになりました(BB, p.19)。
これが成立するためには、成功例が存在しなければなりません。AAメンバーの大半が酒をやめていなかったならば、AAに行って「自分にもできる」と思う人はいないでしょう。(cf. 第9回)
また、アディクションは激しい苦痛や強い苦悩をもたらしているという認識も必要です。飲酒で酩酊している人や、薬でハイになっている人、パチンコにのめり込んでいる人、過食と嘔吐をしている人たちは、その行為から何らかの慰めを得ているのは事実ですが、その行為の過剰さによって、慰め以上の苦痛を味わう羽目になっています。それは強迫性障害の強迫行動が、強迫観念のもたらす不安の解消に役に立っているにしてもその過剰さによって苦痛や苦悩が生じている構図とそっくりです。
なぜ自らに苦痛をもたらす行為がやめられないのか、を説明してくれるのがオブセッションとコンパルジョンという概念です。それらを理解することにより、望んでいない思考や行為を病気によって強制される、というこの病気の本質を理解することができるのです。[LABW#1][LABW#2]
AAの仲間たちの存在やオブセッションとコンパルジョンへの理解は、私たちから学習性無力感を剥ぎ取ってくれますが、同時に私たちはオブセッションとコンパルジョンを自分の力では解決できない、という真の無力と向き合うことになります。それについては次回以降で説明していきましょう。
オブセッションとコンパルジョンの歴史
終わりに、嗜癖におけるオブセッションとコンパルジョンという概念の歴史について簡単に触れます。前述のように、これは、AAのビッグブックでアルコホリズムを強迫観念(obsession)と渇望(craving)の組み合わせとして説明したものが始まりです。AAの共同創始者であるビル・Wは、それらの概念を主治医のシルクワース医師から教えられたことで彼自身の病気を理解しました。それだけでなく、それらの概念は彼がもう一人の共同創始者であるドクター・ボブの回復を手助けする際にも役に立ちました。その結果、強迫観念と渇望はステップ1の中心的な概念として採用され、ビッグブックに詳述されることになりました。

ところで、ビル・WはAAのテキストの主な著者であり、その意味では12ステップの内容を最も熟知した人物であったはずですが、彼は自分が書いた本の内容をメンバーに解説する役割を引受けませんでした。それはおそらく彼が自分という個人が権威化することを避けたかったからだと考えられます。しかし、12ステップをシンプルに分りやすく説明してほしいというニーズは常に存在します。そこで、各地のAAメンバーがステップの説明を試み、それを書籍や小冊子として出版しました。その中には人気を博して、多くのグループやメンバーに愛用された本もあります。例としてエド・W(Edward Webster, -1971)の The Little Red Book や、ドクター・ボブが同じグループのエヴァン・W(Evan W.)に指示して書かせた A Guide to the Twelve Steps of Alcoholics Anonymous などが挙げられます。こうしてAAでは、ビッグブックや12&12などの公式なテキストと並行してメンバーが書いた解説書が使われるようになり、それが現在まで続いています。
公式なテキストの内容は滅多に変更されませんが、AAメンバーの書いた解説書には流行り廃りがあり、ある時期にメンバーに愛用された本も、やがて人気を失い、別のものに取って代わられます。なので、年代ごとに人気のあった解説書を読み比べることで、AAのなかで12ステップの解釈がどのように変化してきたかを知ることができます。
その結論を言うと、1940年代・50年代の解説書では、すでに強迫観念と渇望という概念は重要視されなくなっています。つまり、AAが始まって早々に、それらの概念は重要視されなくなったと思われるのです。しかしビッグブックなどの公式のテキストにはそれらが書かれている以上、完全に忘れ去られたはずはありませんし、もしそうならそれらの概念がNAに引き継がれることもなかったはずです。それでも、これらの二つの概念は注目されなくなり、その状態が1970年代まで続きました。
ところが1980年代以降に書かれたステップの解説書には、この二つの概念がほぼ必ず取り上げられています。そして、それはAAだけでなく、ドーンファームのような施設で使われる資料や、AA以外の12ステップ共同体のテキストにも(用語を変化させつつ)採用されています。つまり1980年代に12ステップの解釈に一つの大きな変化が起きたことは明らかです。
そのような変化が起きた理由はまだ十分調査ができていません。しかし、現段階の仮説として、それはジョー・マキューとチャーリー・Pによって各地で行われた Big Book Comes Alive! というセミナーの影響だと考えられます。12ステップの歴史は、ジョー・アンド・チャーリー以前と彼らによる復興運動以後に大きく分けられるのです。
ところで日本ではどうだったのかというと、日本で現在のAAを始めたジャン・ミニー神父(John J. Meaney, 1930-2007)は、強迫観念と渇望という概念を日本のAAメンバーに伝えませんでした。それはやむを得ないことで、彼がアメリカで回復した1970年代前半にはまだ復興運動は始まっておらず、彼とて「自分がまだ手にしていないものを人に手渡す」(BB, p.240)ことはできなくて当然でした。さらには、その後の日本のAAメンバーたちが本から学ぶことを軽視したために、強迫観念と渇望という概念を知らないままその後の数十年を過ごすことになりました。
また日本ではAAに続いてNAやGAやOAなどの様々な12ステップ共同体も始まりましたが、彼らも日本のAAから多大な影響を被り、本から学ぶことを軽視した結果としてオブセッションとコンパルジョンという概念を獲得できないまま長い時間を過ごすことになりました。この数十年、日本の12ステップ界隈は、江戸時代の鎖国 と同じような情報遮断の環境に置かれ、世界の潮流から取り残されてしまったのです。

しかし国内でもジョー・マキューの書籍の翻訳出版などを通じて、すでに変化は始まっています。例えば2011年に出版された『プログラム フォーユー』は強迫観念と渇望という概念の重要性を強調しつつ、その中身を明確に説明しています。5) すでに鎖国の時代は終わっているのです。しかも、オブセッションとコンパルジョンについて学ぶのに、必ずしもジョーの本を読む必要はありません。なぜなら、各共同体のテキストにはそれが書かれているのですから、そこから学べば良いのです。これはそれを手助けするための連載です。
歴史の話は終わったと言いながら、また歴史の話をしてしまいました。ともあれ、強迫観念と渇望、あるいはオブセッションとコンパルジョンという概念は、新しいものではなく、12ステップの始まりから存在していたものなのです。この連載であなたが初めて接する概念が他にもきっとあるでしょう。なぜそのようなことが起きるのかと言えば、単純に、日本の12ステップ共同体がしばらく前まで鎖国状態に置かれていたからなのです。
- 強迫観念と渇望、あるいはオブセッションとコンパルジョンという概念は、ほとんどの12ステップ共同体のステップ1に採用されている
- アディクションという病気になった人たちは(強迫性障害の人たちと同じように)本人が望んでいない思考や行為を「病気によって」強制されている
- アディクション(依存症)は一次疾患であり、この病気になった原因を取り除いても、病気は解決しない
- この病気の人たちが問題を否認したり、解決を諦めてしまうのは学習性無力感ゆえ
- 学習性無力感を解消することで、無力を認める準備が整う
- American Psychiatric Association(高橋三郎他訳)『DSM-IV 精神疾患の診断・統計マニュアル』, 医学書院, 1996, p.427.[↩]
- American Psychiatric Association(高橋三郎他訳)『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』, 医学書院, 2014, p.240.[↩]
- エドワード・J・カンツィアン他(松本俊彦訳)『人はなぜ依存症になるのか 自己治療としてのアディクション』, 星和書店, 2013.[↩]
- 小林桜児『人を信じられない病 信頼障害としてのアディクション』, 日本評論社, 2016.[↩]
- PFY.[↩]
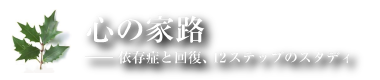


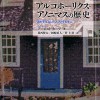

最近のコメント